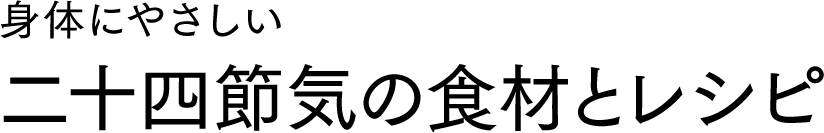寒露は明け方の草木や葉の上につく露が寒さによって凍りそうになる頃です。朝晩はひんやりとする日も多く、日中も段々と涼しい日が増えてきて、少しずつ秋の訪れを感じられているのではないでしょうか。体調を崩したり、風邪を引いたりしやすい時期です。暑い時期によく食べていた冷たい食べ物、飲み物をそのまま食べていると、お腹が冷えます。お腹には免疫を司るリンパ球が多く、冷えると、免疫力の低下に繋がります。うどんやそばは温かくして、飲み物はホットにして、生野菜は温野菜にして、実の野菜よりも根菜を多くしてなど、季節に合わせた食べ方や食材選びをするとよいでしょう。
「かぶ」
季節感があまりなく、旬のわかりにくい野菜のかぶですが、秋と春がおいしい季節です。鈴のような形をしていることから、「すずな」とも呼ばれています。丸い根の部分を食べることが多いですが、皮膚や粘膜の健康維持を助けるビタミンCやβ-カロテンといった栄養成分は葉の方に多く含まれているので、丸ごと調理すると、かぶの栄養を余すことなく摂ることができます。葉は青菜と同じように、和え物や汁物、炒め物、煮物の彩りとして使って頂けます。グリーンスムージーや細かく刻んでふりかけにも活用できます。また、根の部分はほのかな甘みとなめらかな食感が特徴で、大根のような辛み成分が含まれていないので、漬物やサラダなど生食にも向いています。今の時期はぬか床を育てるのに最適な室温です。かぶのぬか漬けで発酵食品を取り入れてみてはいかがでしょうか。


「ざくろ」
一昔前、女性ホルモンが含まれるため更年期障害や抜け毛の防止に良いとして、ブームの沸き起こったざくろ。実際には、女性ホルモンは含まれておらず、女性ホルモンに似た性質を持つ成分が含まれているといわれています。国内での生産はほとんどなく、庭木や山あいの木の実として目にすることがあります。市場に果実として出回っているものは少ないため、ジュースやお酢として売られているものは、手に入りやすいです。ザクロの中には鮮やかな赤色をした種が沢山詰まっているので、子宝に恵まれる縁起の良い果物といわれていますが、実はその種に女性ホルモン様物質が多く含まれています。生の果実が手に入った際には、種も一緒にジュースにするのがおすすめです。

「食用菊」
寒露は菊の花が開き始める頃ともいわれています。食用菊は一年中出回っていますが、この頃の食用菊は香りが良いといわれています。紫色や黄色の花をそのまま料理の飾りに使うことも多くありますが、花びらを取り外して、和え物やお浸し、あんかけ、お吸い物などの彩りとして料理に使うことができます。食べたものをエネルギーに換えるのを助けてくれるビタミンB1、B2が多く含まれていますが、これらは加熱に弱く、さらに加熱し過ぎると花びらの色、風味が落ちてしまうので、茹でる際は少量の酢を加えたお湯でサッと茹で、すぐに水に取るようにしましょう。生のまま食べることもできます。


「ディル」
「魚のハーブ」ともいわれるほど、魚との相性が良い、爽やかな香りを持つハーブです。爽やかな香りの成分は、心を落ち着かせたり、消化を良くしたりするといわれています。日本でも少量栽培されており、イタリアンやフレンチ、ロシア料理などでよく使われています。細かく刻んでスープやサラダに混ぜたり、肉や魚と一緒にソテーしたり、パスタに添えたりといった使い方ができます。油やお酢との相性も良いので、オリーブオイルに漬けてハーブオイルに、ピクルスを作るときに一緒に漬け込んで香りを活かすことができます。秋の夜長を、ハーブを使った素敵なお料理とともにゆっくりと堪能してみてはいかがでしょうか。

「小豆」
寒露の頃、日本の小豆の一大産地である北海道は、収穫期を迎えます。そこから乾燥・調整を行い、店頭で新豆が手に入るのは11月頃です。新米同様、新豆の美味しさは格別で、色は明るく、香りもよく、水分が多いため早く煮えるというのが特徴です。小豆はあんにして食べることが多いですが、この頃の小豆は茹で
たものをサラダやスープ、カレーに入れるというのは如何でしょうか。豆の香りを楽しむことができます。小豆にはカテキン、ルチン、レスベラトロール、アントシアニンなど多くのポリフェノールが含まれています。赤ワインはポリフェノールを多く含むことで有名ですが、小豆に含まれるポリフェノールはそれよりも多いといわれており、抗酸化作用が期待できます。また、小豆は食物繊維が豊富なため、小豆を使ったおやつは腸内環境を整えるのにおすすめです。これらの成分は皮に多く含まれているため、こしあんよりも、粒あんなど皮の付いたままの小豆の方が効率良く摂ることができます。


(文:デザイナーフーズ株式会社)